築年数が火災保険の保険料に与える影響と対策ポイント
- Valuable One
- 2025年6月24日
- 読了時間: 16分
更新日:2025年7月30日
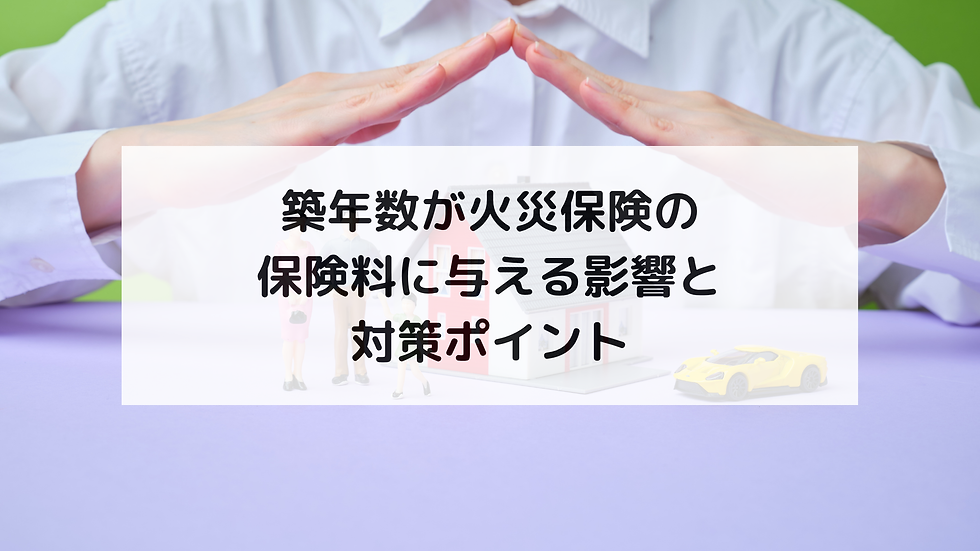
▶︎1. 火災保険と築年数が保険料に与える影響とは?

1.1 築年数が火災保険に与えるリスクの具体例
築年数が進むと、建物の状態が変わり火災保険のリスク評価にも影響が出ます。具体的には以下のようなポイントがあります。
建物の老朽化による耐火性能の低下
外壁や屋根の素材が劣化し、火災が広がりやすくなるリスクが高まる
配線や設備の劣化
古い配線や設備はショートや漏電の原因になり、火災の発生リスクが増す
修繕やメンテナンスの不足
築年数が長いほど修繕が行き届かず、火災や損害の発生リスクが増加する
よくある失敗例とその対策も紹介します。
① 築年数を無視して高い保険料を支払ってしまう
→ 建物の状態に合わせて適切な保険料を見直すことが大事
② 建物の状態を正確に申告しないために保険金が下りにくくなる
→ 正確な申告でスムーズな保険金支払いができる
③ 築年数に合わない補償内容を選び無駄な支出が増える
→ 必要な補償だけを選ぶことで保険料を抑えられる
日常のイメージとしては、築20年以上の住宅で屋根の劣化により火災リスクが高まるケースがあります。忙しい毎日の中でも、定期的な建物点検や修繕で火災リスクを減らせるので、保険料の節約にもつながります。
築年数が増えると建物のリスク評価が高まり、火災保険料に影響が出やすくなることを理解しましょう。
1.2 築年数による火災保険料の変動ポイント
火災保険の保険料は築年数に応じて変動します。築年数が古くなるほど、建物の損害リスクが高いと判断され、保険料が上がる傾向があります。主な変動ポイントは以下の通りです。
築10年未満:比較的建物の状態が良く、保険料は安めに設定されることが多い
築10~20年:老朽化が進み始めるため、保険料が徐々に上昇するケースが多い
築20~30年:建物の劣化が顕著になり、保険料はさらに高くなる傾向がある
築30年以上:保険会社によっては新規加入を断る場合もあり、保険料がかなり高額になることがある
よくある失敗例は次のとおりです。
① 築年数が上がっているのに以前と同じ保険料で契約し続けてしまう
② 築年数を理由に新規加入が難しいと諦めてしまう
③ 築年数だけで判断し、建物の補修状態を無視してしまう
これらの失敗を防ぐためには、築年数とともに建物の状態を正確に把握し、複数の保険会社で見積もりを比較することが重要です。たとえば、築25年の住宅でもきちんとメンテナンスされていれば保険料の抑制につながるケースがあります。
築年数による保険料の変動は建物の劣化リスクに基づいているため、定期的な状態チェックと見直しが保険料節約のカギになります。
▶︎2. 築年数が古い建物の火災保険加入における影響と現状

2.1 築年数が古い物件の新規加入の難しさ
築年数が古い建物では、火災保険の新規加入に関して多くの方が困っています。特に築30年以上、築40年以上の住宅は保険会社がリスクを高く評価し、新規加入を断るケースも少なくありません。これは建物の老朽化が火災やその他の損害リスクを増やすためです。
一般的によくある失敗例を挙げると次のようになります。
築年数だけで加入を諦めてしまう
築年数が古いからといって全ての保険会社で加入不可とは限りません。複数の会社を比較することが重要です。
新築時と同じ保険会社に断られたまま他社に相談しない
一社で断られても、他の保険会社なら加入可能な場合があります。選択肢を広げることがポイントです。
建物の具体的な状態やメンテナンス履歴を伝えずにリスクが誤解される
正確な情報提供がなければ、保険会社はリスクを過大評価し加入を断る可能性が高まります。
築年数が古い物件でも新規加入を成功させるためのポイントは以下の通りです。
複数の保険会社に問い合わせて、加入可能な会社を探す
ネット専業だけでなく、対面で相談できる会社も検討しましょう。
建物のメンテナンス履歴や改修履歴を詳しく伝える
過去の修繕や補強工事がリスク軽減につながり、加入条件が緩和されることがあります。
専門の保険代理店や保険コンサルタントに相談する
築古物件の取り扱いに詳しいプロに依頼することで、スムーズな加入が期待できます。
建物の現状を定期的に点検し、記録を残す
点検結果を保険会社に提出できると、信頼度が上がり加入しやすくなります。
具体例として、築35年の住宅でも、定期的な屋根の修繕や耐震補強が記録されていたケースでは、対面で相談した保険会社で加入できた事例があります。こうした情報は忙しい日常でも整理しておくと大きな助けになります。
築年数が古くても、正しい情報提供と適切な相談先の選択で火災保険の新規加入は可能です。諦めずに複数の選択肢を検討しましょう。
2.2 築年数別に見る火災保険加入の条件例
築10年未満の建物
新築に近いため、建物の状態が良好でリスクが低い
保険料は比較的安く、ほとんどの保険会社で新規加入が可能
補償内容も幅広く選べることが多い
築10年~20年の建物
建物の老朽化が徐々に進み始める時期
保険料がやや上昇する傾向がある
一部の保険会社では建物の状態によって加入条件が厳しくなる場合がある
こまめなメンテナンス記録が加入審査で有利になることがある
築20年~30年の建物
建物の劣化が目立ち始める時期でリスクが高まる
保険料はさらに上昇し、加入条件も厳しくなることが多い
一部の保険会社では新規加入を断るケースも増える
建物の状態を詳細に申告し、必要な補償を選ぶことが重要になる
築30年以上の建物
老朽化が進み、火災や損害のリスクが大幅に上昇
多くの保険会社で新規加入を断る場合がある
保険料はかなり高額になるケースが多い
建物の修繕履歴や補強工事の有無が加入の可否を左右する
対面型の保険代理店で個別対応が必要になることが多い
注意すべきポイント
築年数だけで判断せず、建物の状態を正確に伝えることが重要
加入条件は保険会社によって異なるため、複数の会社を比較することが必須
築古物件は契約内容の見直しや補償の選択が保険料節約の鍵になる
よくある失敗例
築30年以上で新規加入をあきらめてしまう
建物の修繕歴を把握せず加入申込をする
条件の異なる保険会社を比較せずに決めてしまう
築年数が増えるにつれて加入の難易度は上がりますが、適切な情報提供と複数社比較を行うことで加入できる可能性は十分あります。たとえば築35年の物件でも、細かなメンテナンス記録を提出し、対面での相談をした結果、加入できた例もあります。
築年数に応じた火災保険の加入条件を理解し、情報を整理して複数社から見積もりを取ることが成功のポイントです。
▶︎3. 築年数が火災保険料に与える影響とその背景

3.1 築年数増加による保険料上昇の要因
築年数が増えると火災保険料が上がる理由は主に建物のリスク評価の変化にあります。建物の老朽化が進むことで火災や自然災害の被害が大きくなる可能性が高まるため、保険会社はそれを保険料に反映させます。具体的な上昇要因は以下の通りです。
耐火性能や耐久性の低下
古い建物は建築基準法の改正前に建てられている場合が多く、耐火・耐震性能が新築に比べて劣ることが多い
設備の老朽化によるリスク増加
電気配線やガス設備などが劣化し、火災発生のリスクが高まる
修繕や補修の不足
定期的なメンテナンスが行われていない場合、火災や水害のリスクがさらに上昇する
市場価値の下落と補償金額の変動
築年数が経つにつれて建物の評価額が下がるため、保険金額設定に影響が出るが、リスクは上がるため保険料は必ずしも下がらない
よくある失敗例
築年数によるリスク上昇を理解せず保険料の見直しをしない
建物の老朽化を軽視し必要な補償を外してしまう
保険会社のリスク評価基準を把握せず加入する
築年数が上がると保険料は平均で20〜30%ほど増えるケースもあります。たとえば、築15年の建物と築30年の建物を比較すると、築30年のほうが保険料が2割以上高くなることがあります。
築年数による保険料上昇の背景を理解し、定期的に保険内容の見直しを行うことが大切です。
3.2 築年数で異なる具体的な火災保険料の差
築10年未満の火災保険料の特徴
建物の状態が良く、火災リスクが低いため保険料は比較的安い
新築割引や長期契約割引が適用されることが多い
さまざまな補償プランから選べる自由度が高い
築10年〜20年の火災保険料の傾向
建物の劣化が徐々に進み始め、保険料がやや上昇
補修履歴がある場合は割引が受けられる可能性がある
一部の保険会社で保険料の見直しが必要になることも
築20年〜30年の火災保険料の変動
老朽化の影響で保険料が数割上がる場合が多い
補償範囲を見直し必要な補償を選ぶことが保険料節約のポイント
一部保険会社では条件付き加入や保険料割増が適用される
築30年以上の火災保険料の特徴
建物の老朽化リスクが高く保険料が大幅に上がる
新規加入を断られるケースが増えるが、条件付きで加入可能な場合もある
補修や補強工事の証明があれば保険料が抑えられることもある
よくある失敗例
築年数に応じた保険料差を理解せず旧契約のまま継続してしまう
築古物件に合わない補償内容を選び無駄な支出が増える
複数社の見積もりを取らずに保険料が高い契約を続ける
築年数が上がるほど保険料は平均で20〜40%程度上昇する傾向があります。たとえば築15年の建物と築35年の建物を比較すると、築35年のほうが保険料が約3割高くなることがあります。
築年数による具体的な保険料差を理解し、定期的に見積もりを比較して最適な保険を選びましょう。
▶︎4. 築年数が古くても火災保険に加入する方法と対策
4.1 築年数を考慮した火災保険会社の選び方
築年数が古い物件の場合、火災保険の加入や更新において、保険会社の選択は非常に重要です。築古住宅はリスクが高いと評価されるため、取り扱いに差が出やすく、適切な選択が必要です。以下に、築年数を考慮した保険会社の選び方のポイントを詳しく解説します。
築古物件の取り扱いに強い保険会社を選ぶ
対面型保険代理店の利用がおすすめ
対面で相談できる代理店は、築年数が古い建物でも建物の状態を詳しく確認し、柔軟な対応が可能です。担当者が直接状況を把握するため、ネット専業の保険会社よりも審査が通りやすい傾向があります。
ネット専業保険会社の築年数制限に注意
ネット専業の保険会社は、築年数制限が厳しい場合があります。例えば築20年や30年を超えると新規加入不可になるケースもあり、築古物件には向かない場合が多いです。
専門知識を持つ担当者がいる保険会社を選ぶ
築古物件のリスクを正しく評価できる知識や経験がある担当者がいる会社を選ぶと、無駄な保険料を抑えつつ必要な補償を得やすくなります。
保険商品の補償内容をしっかり確認する
築年数に応じた補償の必要性を理解する
古い建物は火災以外にも、水漏れや老朽設備の故障リスクが高いため、補償内容の見直しが大事です。例えば、漏水補償や設備故障の特約が必要になるケースがあります。
無駄な補償を減らすことで保険料を抑える
必要のない補償を付けると保険料が上がるため、建物の実情に合わせた補償設計が大切です。必要最低限の補償を選び、不要な特約は外す工夫をしましょう。
免責金額の設定で保険料を調整する
免責金額を高めに設定することで保険料を抑えることができますが、自己負担額が増えるためバランスを考えて決めましょう。
保険料の見積もりを複数社で比較する
築年数が古い物件は保険料差が大きい
保険会社によってリスク評価や割引制度が異なるため、同じ築年数でも保険料に大きな差が出ます。複数の会社から見積もりを取り、比較することが不可欠です。
ネット保険と対面型保険代理店の両方から見積もりを取る
ネット保険は料金が安い場合がありますが、築古物件には向かないことも。対面型代理店は対応が柔軟で、保険会社との交渉も期待できます。両方から見積もりを取り、メリット・デメリットを比較しましょう。
代理店を通すと交渉や疑問点の相談がスムーズ
代理店の担当者は保険会社とのやり取りを代行し、条件交渉や保険内容の説明をしてくれます。築年数が古い物件の場合、こうしたサポートは大きな助けになります。
よくある失敗例
ネット専業の保険会社だけで選んで加入を断られる
築年数制限で新規加入できないケースが多いので、複数の選択肢を検討しないと加入できません。
補償内容を理解せず高額な保険料で契約してしまう
建物の状態に合わない補償を選び、無駄な費用を払い続けることがあります。
見積もりを一社だけで決めてしまう
保険料や条件の違いを比較しないため、損をする可能性が高いです。
築年数が古い物件は火災保険の選び方が重要で、柔軟に対応してくれる対面型の保険代理店を利用するのが有効です。複数社の見積もりを比較し、補償内容や免責金額のバランスを考えながら選ぶことで、適切な保険料で必要な補償を得ることができます。忙しい中でもこれらのポイントを押さえて検討すれば、築古物件の火災保険選びがスムーズになります。
築年数を踏まえ、信頼できる保険会社と相談しながら最適なプランを選びましょう。
4.2 築年数を踏まえた加入時のポイントと注意点
築年数が古い建物に火災保険を加入する際には、いくつかの重要なポイントと注意点があります。これらを押さえておくことで、適切な補償を確保しつつ無駄な保険料を避けることができます。以下に具体的に解説します。
建物の状態を正確に申告する
劣化状況や修繕歴を詳しく伝えることが大切
築年数だけでなく、屋根や外壁の補修、配線や設備の更新履歴を正確に申告しましょう。これにより保険会社のリスク評価が適正になり、保険料の見積もりが適切になります。
虚偽や不十分な申告は保険金の支払いトラブルにつながる
不正確な情報は契約後の事故対応時に保険金が下りにくくなる原因になるため、正直に申告することが重要です。
点検や修繕記録を整理しておくとスムーズ
日常的に建物の点検やメンテナンス記録を残し、保険加入時に提出できるよう準備しておくことがおすすめです。
必要な補償内容を見極める
築年数に応じたリスクを考慮した補償選択が必要
火災以外にも水漏れや設備の故障リスクが高い築古物件は、それらをカバーする補償を選ぶことがポイントです。
不要な補償を減らして保険料を抑える
逆に古い建物でも必要のない補償が含まれていると、無駄な支払いになるため補償内容を精査しましょう。
免責金額の設定で保険料とリスクをバランス調整
免責額を高めに設定することで保険料が安くなりますが、自己負担増になるので注意が必要です。
契約期間と更新時の見直し
長期契約のメリットと注意点
長期間の契約は保険料割引がある場合がありますが、建物の状態変化に対応しづらいため定期的な見直しが大事です。
更新時には築年数の増加や補修状況を再確認
契約更新時に最新の建物状態を伝え、保険料や補償内容の見直しを行いましょう。
補償内容の過不足をチェック
必要な補償が足りない、または不要な補償が含まれていることがないか、定期的に確認する習慣をつけることが安心につながります。
よくある失敗例
建物の老朽化を申告せずにトラブルになる
必要以上の補償をつけて保険料が高くなる
契約後に保険内容を見直さず無駄な費用を払い続ける
築年数が古い住宅では、こうしたポイントを踏まえて加入や更新を進めることが重要です。たとえば築25年の住宅で、過去の修繕履歴を詳細に申告し、必要な補償に絞った結果、トラブル発生時にもスムーズに保険金が支払われたケースがあります。
築年数を踏まえた正確な申告と補償内容の見極めが、火災保険の安心と節約につながります。
▶︎5. 築年数の影響を踏まえた火災保険の見直しと最適化
5.1 築年数に応じた定期的な火災保険の見直し方法
築年数の変化に合わせた見直しの重要性
建物は時間とともに劣化し、リスクが変わるため保険内容も定期的に更新が必要
築10年ごとに一度は契約内容を見直すのが理想的
建物の改修や補修履歴があれば保険料の見直しで節約につながる
見直し時にチェックすべきポイント
保険金額が現在の建物価値に合っているか
補償内容に不要な項目が含まれていないか
免責金額や特約の設定が適切か
他社の保険料やサービスと比較して割高でないか
見直しをスムーズに進めるコツ
建物の状態を細かく記録しておく
複数の保険会社から見積もりを取り比較検討する
専門の保険代理店に相談して最適プランを提案してもらう
よくある失敗例
築年数が進んでも保険内容を見直さず古い契約のままにしてしまう
建物の修繕履歴を把握せず見直しの機会を逃す
見積もり比較をせず更新して保険料が高くなる
築年数に応じた火災保険の見直しは、保険料を抑えつつリスクに備えるために非常に効果的です。例えば築15年の住宅で補修工事後に見直したことで、保険料が20%以上安くなったケースもあります。
築年数を考慮し、定期的に火災保険の契約内容を見直す習慣をつけることが大切です。
5.2 築年数を考慮した保険料の比較と選び方
築年数による保険料の差を理解する
築年数が古い建物ほど保険料は高くなる傾向があるため、複数の保険会社で比較することが重要
保険料だけでなく補償内容や免責条件も考慮し総合的に判断する必要がある
補修歴や耐震補強の有無で割引が適用されるケースもあるため情報収集が大切
複数の保険会社から見積もりを取るメリット
保険会社ごとにリスク評価や割引制度が異なるため、見積もり結果に差が出る
ネット保険と対面型保険代理店の両方から見積もりを取り、比較すると選びやすい
代理店を通すことで交渉や疑問点の相談がスムーズになる場合が多い
保険料節約のポイント
不要な補償を見直して削減する
免責金額を適切に設定し、保険料負担を調整する
建物の修繕や補強工事を行い、保険会社へ適切に申告する
よくある失敗例
複数社の見積もりを取らずに最初の保険会社で決めてしまう
保険料だけで選び、補償内容を疎かにする
建物の補修歴を申告せず割引を受け損ねる
築年数の影響を考慮して複数社から見積もりを比較することで、保険料を20%以上節約できることもあります。たとえば築25年の住宅で対面型代理店を利用し、最適プランに切り替えた結果、年間保険料が大幅に下がった事例があります。
築年数を踏まえた保険料の比較と選択は、無駄なコストを抑えつつ必要な補償を確保するために欠かせません。
▶︎6. まとめ:火災保険における築年数の影響を理解し最適な選択を
築年数は火災保険の保険料や加入条件に大きく影響します。古くなるほど建物のリスクが高まり、保険料が上がったり新規加入が難しくなったりするのが一般的です。しかし、築年数だけで判断せず、建物の状態や修繕履歴を正確に申告し、複数の保険会社から見積もりを比較することで、最適な火災保険を選べます。
主なポイントは以下の通りです。
築年数が上がると火災リスクが増え、保険料は20~40%程度高くなる場合が多い
築古物件でも適切な情報提供と相談で加入できる保険会社は存在する
定期的な見直しで保険料の節約と補償内容の最適化ができる
補修履歴や耐震補強の有無が保険料や加入条件に良い影響を与える
日常生活のなかで、築年数が進んだ住宅の火災保険を見直すことで、年間の保険料が大幅に節約でき、かつ万一のときの補償もしっかり確保できます。忙しい中でも数社の見積もりを比較し、専門家に相談する時間を作ることが将来的な安心につながります。
築年数の影響を正しく理解し、適切な火災保険選びと定期的な見直しを行うことが大事です。
▶︎築年数に合わせた火災保険の見直しはValuable Oneに相談を
築年数による火災保険料の変動や加入条件の違いを踏まえた見直しが必要です。プロの視点で最適なプランをご提案し、保険料の節約にもつなげます。
まずはお気軽にごValuable Oneに相談ください。
コメント